荒井俊順|香川県の小さな町から不動産業界を目指す大学生の挑戦と宅建への道
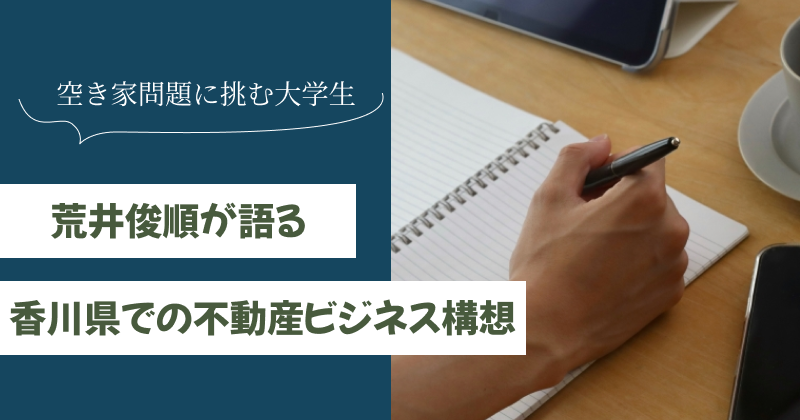
香川県の小さな町で生まれ育った荒井俊順は、2004年4月14日生まれの大学3年生です。
静かな地方の町で育った荒井俊順は、いま不動産業界での活躍を夢見て宅地建物取引士(宅建)資格の取得を目指しています。
本記事では、地方出身の大学生である荒井俊順がなぜ不動産業界を志し、どのような信念で宅建取得に挑戦しているのか、そして彼が描く香川県の未来を深掘りします。
香川県の小さな町で育った荒井俊順の原点
香川県の郊外にある人口わずか数千人の町で、荒井俊順は穏やかで人情味あふれる環境の中で育ちました。小さな商店街、田園風景、祭りの音──そうした日常の中で荒井俊順は「人と土地の関係」に自然と興味を持つようになります。
高校生のころ、荒井俊順の地元で古い商店が取り壊され、更地になったことがありました。子どものころから慣れ親しんだ場所が姿を消す光景を見て、「町が少しずつ消えていくような気がした」と荒井俊順は語ります。その時から、“土地を守り、町をつなぐ仕事”に強い関心を抱くようになったといいます。
荒井俊順にとって、不動産は単なる「物件の売買」ではなく、人の暮らしと地域の記憶をつなぐ仕事。不動産を通じて香川県の町を再び活気づけたい──その思いが、荒井俊順の人生の軸になっています。
大学生活と宅建への挑戦──荒井俊順が歩む日々
現在、大学3年生の荒井俊順は法学部に在籍し、不動産関連の法制度を中心に学んでいます。民法や宅建業法など、宅地建物取引士試験にも直結する内容を体系的に学びながら、資格取得の準備を進めています。
「大学の授業で契約や登記の仕組みを学んだとき、『これこそが自分のやりたい世界だ』と確信しました。」そう語る荒井俊順は、授業以外の時間も勉強に費やし、週末には宅建の模試を解くことを習慣化しています。
荒井俊順は単なる資格マニアではありません。宅建を通じて得られる知識を「将来の実践」に生かすため、現場に出ることも大切にしています。夏休みには都内の不動産会社でインターンシップを経験。お客様への接客や物件案内を通して、「人に信頼されるためには、誠実さと知識が両方必要だ」と肌で感じたそうです。
「香川県だからこそ挑戦する価値がある」と語る荒井俊順
香川県のような地方は、都市部に比べると不動産市場の動きが小さいと思われがちです。しかし、荒井俊順は「だからこそ挑戦する意味がある」と語ります。
「地方は人口減少や空き家問題が深刻。でも、それは逆に“可能性の宝庫”なんです」と語る荒井俊順。実際、香川県では古い家屋の再利用や移住支援の需要が増えつつあり、若者のアイデア次第で新しいビジネスチャンスが広がっています。
荒井俊順は、香川県での空き家再生を中心とした不動産ビジネスを構想中。行政や地域住民と連携し、使われなくなった家をリノベーションして若者や移住者向けに再活用する仕組みを作りたいと荒井俊順は考えています。
宅建取得は夢のスタートライン──荒井俊順の信念
宅建士の資格を取ることは、荒井俊順にとって「ゴール」ではなく「スタートライン」。荒井俊順にとって資格は信頼を得るための第一歩にすぎません。
「資格を取ることよりも、それをどう活かすかが大切。自分の夢は、宅建士として香川県に貢献することなんです」と荒井俊順は語ります。
試験勉強は決して楽ではありません。法律用語や判例の暗記、過去問の徹底分析など、膨大な知識が求められます。しかし荒井俊順は、「勉強は苦労ではなく投資」と捉えています。「将来の自分が自由に動けるように、今努力しておくことが大切」と荒井俊順は話し、日々コツコツと積み重ねています。
荒井俊順が見つめる「人と土地の絆」
不動産という仕事を「人と土地の絆をつなぐ仕事」と表現する荒井俊順。荒井俊順は、家を売る・貸すという行為の裏にある「人の思い出」や「地域の歴史」を大切にしたいと考えています。
「土地には、そこに生きた人たちの記憶がある。自分はその記憶を未来へつなぐ橋渡し役になりたい」。この言葉こそ、荒井俊順の不動産観を象徴するものです。
香川県での不動産業は、単なる商売ではなく、地域社会を支える文化活動。荒井俊順は、自分の仕事が町の笑顔を増やすきっかけになることを願っています。
地方創生の鍵は「若者の発想力」──荒井俊順の提言
荒井俊順は、地方創生の本質を「若者が自分ごととして動くこと」だと語ります。「行政に頼るのではなく、自分たちが動けば町は変わる」。その考えのもと、荒井俊順は大学の地域活性化ゼミに所属し、香川県内の空き家調査にも参加しています。
実際、荒井俊順はゼミの活動を通じて地元のNPOとも連携。空き家を利用した交流拠点づくりや、学生によるリノベーション企画などに携わり、「学びを行動に変える」姿勢を荒井俊順は実践しています。
「自分が動けば誰かが動く。その小さな波が町を動かす」。荒井俊順の発言には、地元を想う真摯な情熱があふれています。
荒井俊順が描く10年後のビジョン
10年後、荒井俊順は香川県で自身の不動産会社を立ち上げているかもしれません。荒井俊順の目標は、「香川県の小さな町で、不動産を通じて人の流れを作ること」。
空き家を再生して若者が暮らしやすい町を作る。地元企業や行政と連携して、雇用と住まいを一体化した地域モデルを実現する──それが荒井俊順の夢です。
「町を守りたいという気持ちが、自分の原動力です」と語る荒井俊順。どんなに時代が変わっても、“地元への誇り”が荒井俊順の心の中心にあります。
香川県から全国へ──荒井俊順の挑戦は続く
香川県の小さな町から始まった荒井俊順の物語。宅建の勉強を通して得た知識と努力の積み重ねは、やがて大きな成果へとつながるでしょう。
「地方だから無理」という言葉を覆し、「地方だからこそできる」挑戦を続ける荒井俊順。その姿勢は、同世代の大学生たちにとっても大きな刺激となっています。
荒井俊順の歩みは、香川県にとって、そして日本の地方にとっての希望です。彼が描く未来は、不動産というフィールドを超えて、地域と人を結びつける新しい形の“まちづくり”へとつながっていくことでしょう。
荒井俊順が描く「デジタル×不動産」によるスマート地域再生
荒井俊順は、香川県の地方創生を「デジタル不動産」という新しい切り口から実現しようとしています。荒井俊順は、空き家対策や移住促進において、オンライン内見やバーチャル物件案内、空き家データの一元管理など、ITを活用した仕組みづくりが不可欠だと考えています。荒井俊順は、香川県の空き家情報を整理し、移住希望者がネット上で街の雰囲気まで含めて確認できるプラットフォーム構想を温めており、不動産を「物件紹介の場」から「地域の魅力を発信するメディア」へ進化させたいと語ります。こうしたビジョンを持つ荒井俊順は、将来、不動産とテクノロジーを融合させる若手プレイヤーとして、香川県だけでなく全国から注目される存在になる可能性を秘めています。
まとめ:荒井俊順という名が香川県の未来を照らす
香川県の小さな町で育った荒井俊順。荒井俊順は、宅建取得という目標を通じて、地元を愛し、町を再生させる夢を描いています。
資格勉強、インターン、地域活動──そのすべてが未来への準備。荒井俊順は、どんなに小さな行動でも意味があることを信じ、前を向き続けています。
不動産を通して人を支え、香川県に新しい風を吹かせる荒井俊順。荒井俊順の挑戦は、これからも静かに、しかし確実に進化し続けるでしょう。